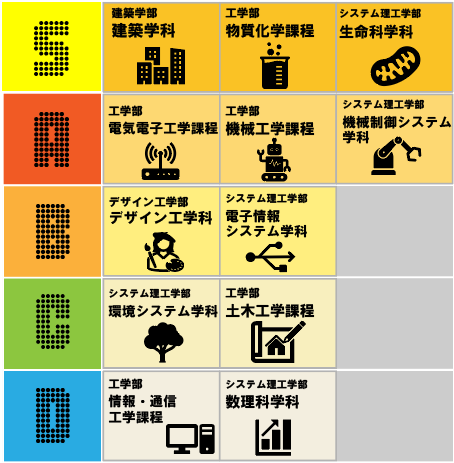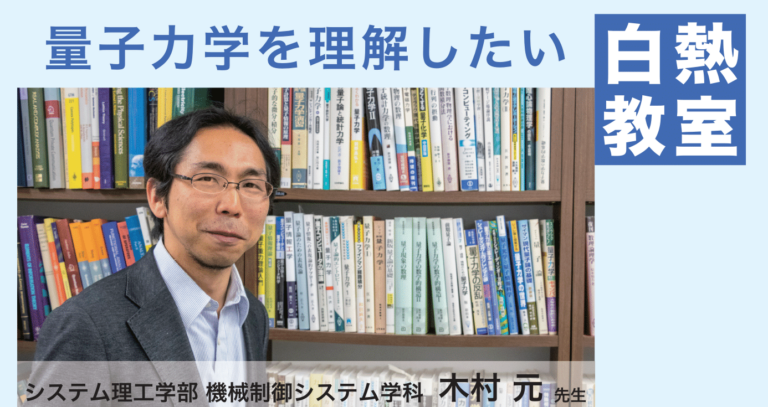2025年春号_vol.52 収録

1993年4月 国際基督教大学 教養学部
1998年4月 東京大学大学院 総合文化研究科
2000年 4月 (株)日立製作所
2018年4月 芝浦工業大学 システム理工学部 教授
今回の白熱教室はシステム理工学部生命科学科の佐藤大樹教授にお話を伺いました。なかなかイメージしづらいヒトの脳機能の研究について分かりやすく教えてくださいました。また、研究者になるまでの経緯や私たちへのアドバイスなども聞かせていただきました。
システム理工学部は2026年度から課程制となります。応用脳科学研究室は2025年現在の学科制では生命科学科生命医工学コースの研究室ですが、課程制導入後は生命科学課程スポーツ工学コースの研究室となりますのでご注意ください。
研究内容について教えてください
応用脳科学研究室では、脳科学の視点からヒトの健康やパフォーマンスの向上を目的として研究を行っています。特に、脳科学の知見を工学に応用することで、これらの達成を目指しています。脳波や機能的近赤外分光法(fNIRS)などの脳機能イメージング技術を用いて実際にヒトレベルでの実験を行うことで、脳のどの部位がどのくらい活性化しているかなどを可視化することができます。今回は現在研究室で行っている研究のうち、緊張状態のパフォーマンスについての研究、精緻な手指の運動と認知機能の関係についての研究について紹介します。
一つ目の緊張状態におけるパフォーマンスについてお話しします。このときの緊張状態と は、心理的なプレッシャーがかかっている状態を指しています。スポーツなどを行う際、普段の練習では上手くいくことが、大事な大会などの場面ではうまく発揮できないといった経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。本研究室では、このような状態のヒトの脳機能を計測します。具体的な実験方法としましては、ダーツを行うヒトの脳活動をfNIRSで測定します。ダーツは十分に練習を行い、ダーツの的と投げる場所は参加者が8割成功するくらいの距離で設定します。すなわち練習通りやれば成功して当然といった状況です。この条件下で、本番のダーツを行わせます。このとき、「10回成功したら賞金5000円、一度でも失敗したら賞金は無し」と伝えます。すると8割成功するはずのダーツの成功率が大幅に下がるのです。脳血流信号や心拍を測定することで、このようなメンタルスポーツにおける緊張状態の可視化を目指しています。
二つ目の精緻な手指運動と認知機能の関係についてお話しします。子どもの手指運動と知的能力の発達には関係があることが知られています。また、高齢者になると、加齢とともに運動能力も認知機能も衰えていきます。これらのことから、精緻な手指運動を行う際、通常の運動時に活性化する運動野という場所以外に、認知機能と深く関与する前頭前野にも活動が見られるのではないかと考えました。こちらも先ほどと同様に、fNIRSを用いて、小さな部品を組み立てるような細かい作業を行うときの脳活動を測定します。これらの研究により、認知機能の発達を促したり、加齢による認知機能の低下を抑えたりするような、手指運動を誘発する玩具や道具の開発に繋げられればと考えています。
研究者を志した経緯を教えてください
元々教育というものに興味を持っていました。学校という雰囲気が好きだったことや、ヒトの成長を見守りたいという気持ちがあったのだと思います。また、ヒトの意識というものに興味があったため、大学は心理学を専攻しました。3年生の時に心理学実験演習という授業があり、仮説を立てて実験をデザインしたり、データを取って統計的に結果を出したりする作業に面白さを感じるようになりました。そして、いずれは大学教員になりたいという思いから大学院に進学しました。修士を卒業した後は大学ではなく日立製作所の研究所に就職し、そこで工学の博士号を取ることができました。日立製作所には18年間勤めましたが、元々なりたかった大学教員の道に進みました。企業でも研究をすることができますが、大学の研究は自由度が高いという点が魅力的であると感じます。
学生へのメッセージをお願いします
「食わず嫌いせずにとりあえず食べてみる」ことです。大学は学年が上がるにつれて学ぶことが専門的になっていくとともに、専門以外のことを学ぶ機会も少なくなります。だからこそ専門以外の本などに触れることが大事になってくるのではないかと思います。勉強に限らずとも、やるか迷うものはやってみる、興味がないことでも誘われたらやる、といったようにフットワーク軽くいろいろなことに挑戦してほしいと思います。やってみると楽しかった、無理だった、どちらにしろやることで初めて気づくことができます。私自身は、大学生のころバックパッカーをしていて、中国から入り、5ヶ月かけてアジアを一周したこともあります。学校や会社など、組織にいると自分にはそこしかないのだと思い込んでしまうことがありますが、枠を外すと全然そんなことはないと気づくことができ、視野を広げる良い経験になりました。現在も研究室内で読書会を開いたり、学生とハーフマラソンに挑戦したり、新しいことにチャレンジしています。
応用脳科学研究室をもっと詳しく知りたいと思った方は、是非インスタグラムをチェックしてみてください!